法務の仕事をしていくうえで、持っていた方がよいと感じた知識について、あれこれ考えていきたいと思います。今回は「ファイナンス知識」について取り上げてみます。
法務が知っておくべきファイナンス知識のレベル感は?
法務が知っておくべきファイナンス知識のレベル感としては、経営企画室などの専門部門や営業や役員などからのファイナンスに関連する相談についていけるという程度の知識で十分です。
あまり深い知識を追求する必要はありません。
例えば、経営企画室から「投資型のビジネス」の相談を受ける際には、「現在価値」とか「割引率」といった言葉が使われることがあります。
こうした言葉がわからないと、彼らの話についていけません。
ついていけていないことは表情や受け答えに現れてしまいますので、簡単にバレてしまいます。そうなると、法務部への信頼を喪失することにもつながりかねません。
もちろん、わからない言葉が出てくれば相談者にその場で聞けばよいのですが、あまり何度も話の腰を折るようなこともしたくありませんので、基本的な知識や言葉については理解を進めておくに越したことはありません。
投資型のビジネスとは?
私は過去に2つの事業会社を経験していますが、そのいずれにおいても原材料(化学薬品)を取り扱う部門がありました。
近時の化学薬品の市場はいわゆる成熟市場と化していることから、品質面での差別化は難しいという状況になっています。
こうした状況においてよく使われる手法が「投資型ビジネス」です。私が所属した2つの事業会社の双方で行われていましたので、この業界ではごく一般的な手法なのかもしれません。
具体的には、自社の化学薬品を購入してもらう見返りとして、無償で客先へ投資を行うというものです。
投資として典型的なものは、自社が販売した化学薬品専用の保存用タンクです。これを自社の費用負担で客先の敷地内に設置するというものです。
これにより、自社以外の化学薬品を購入しづらい状況を作り、競合先からの購入を排除しようという手法です。
一定期間自社から化学薬品を購入してもらうことで、投資分を回収していくスキームになりますので、自社の化学薬品を一定期間継続して購入してもらうという条件を受け入れてもらう必要があります。
昔の携帯電話の販売スタイル(=携帯電話そのものは1円として、契約期間を2年縛りとするなど)に近いものといえるかもしれません。
投資型ビジネスへの法務部の関わり方
この投資回収が得られるのがいつになるのか?という検討は営業や経営企画室が目を光らせる部分ですが、この投資を会社方針に沿った期間内で確実に回収できるようにするための契約書の起案に法務部も深く関わることになります。
その起案に関する打ち合わせの際に、相談者からよく出てくるキーワードが、冒頭で挙げた「現在価値」や「割引率」といったものです。
元の会社で初めてこうした案件の相談を担当した際には、私自身これらの言葉の意味をよく理解できていませんでした。
このことを経営企画室の担当者から見透かされ、説明の途中で「この話、ついて来れています?」といったことを言われてしまい、大変恥ずかしい思いをしました。
この経験から、法務部という部門は、契約や法令に関する知識だけではなく、事業に関わる幅広い知識が求められているということを痛感しました。
それからは、ファイナンスに限らず、経営学、マーケティング、マネジメント、製品知識、競合製品、客先製品、保険、貿易、知財、哲学、歴史、英語、中国語など幅広い知識を身につけようという意識をもって取り組むようになりました。
当然のことながら、相談者の方が実践的な知識は上ですので、それを超えるような深い知識などは不要だと思います。
むしろ、そこまでの知識を持ってしまうと変にマウントを取ろうという意識が働いてしまい、かえって相談者の気分を損ねることにも繋がりかねないとさえ思います。
もっとも、相談者に「何も知らないなこの人は!」という意識を持たれてまうと、相談をすべき相手として相応しくないという印象を与えかねませんので、基準としては「相手の話についていける程度の基礎知識について、本質的な理解ができている状態」にまで持っていけていれば十分なのではないかと感じています。
法務部員にお勧めの本
この「基礎的な知識の本質的な理解」を身につけるには書籍が手っ取り早いと思います。
私の場合は、「実況ファイナンス教室」(グロービス)という本を読みこみました。
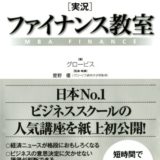
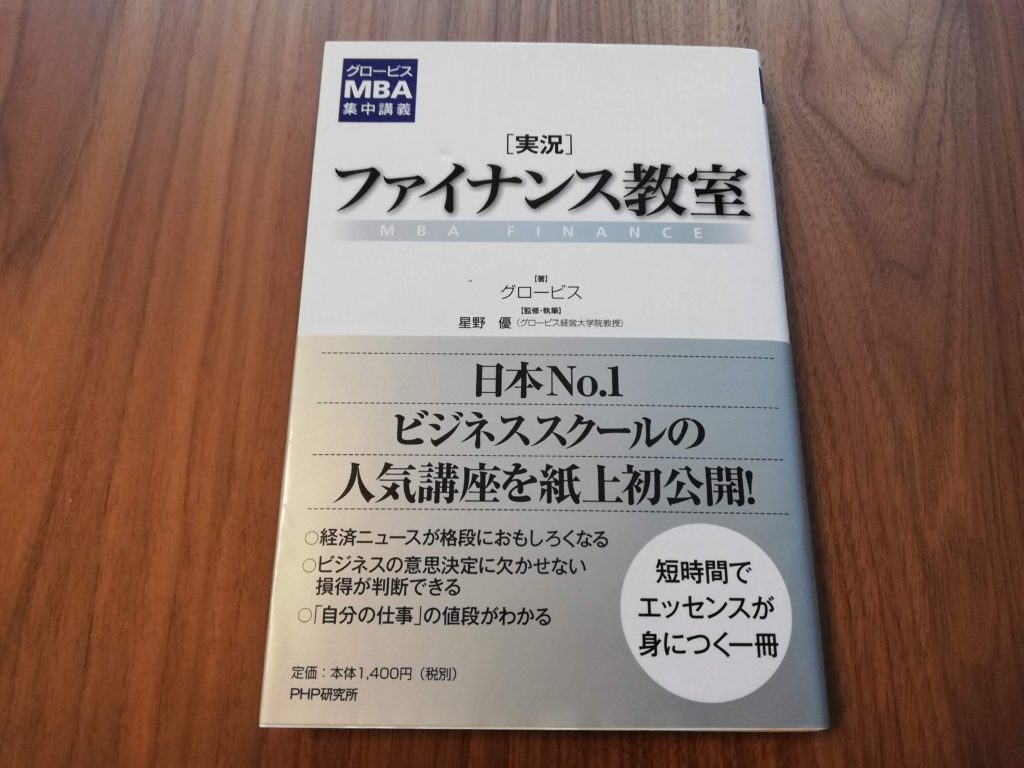
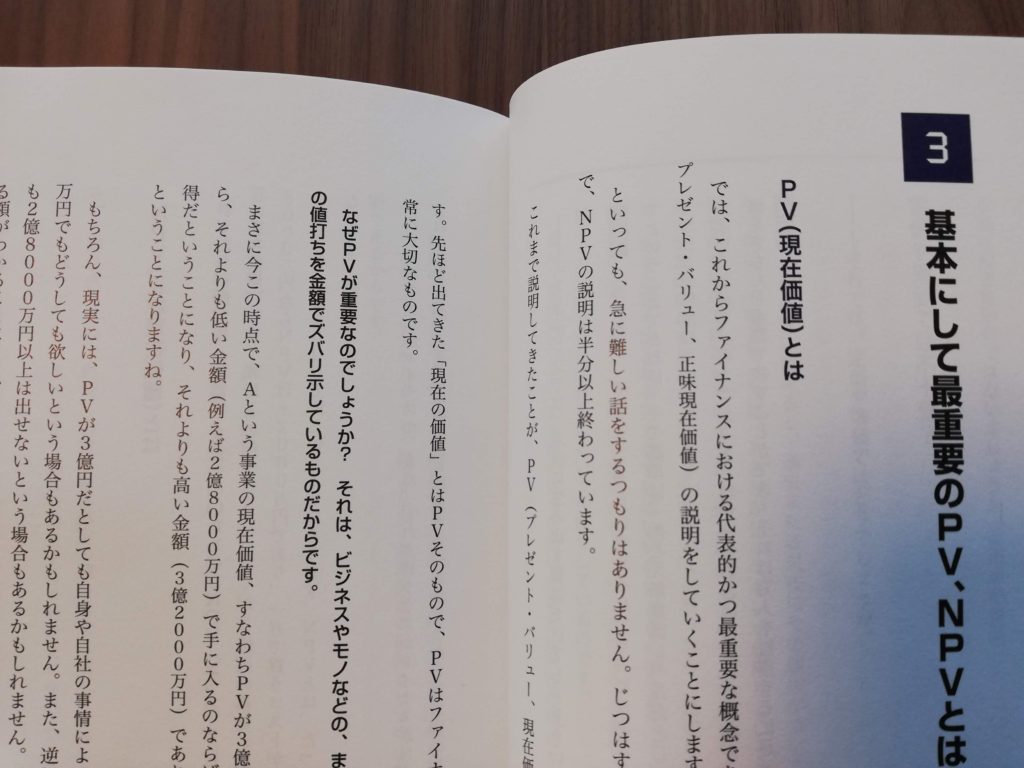
私は新卒で入社した企業が金融系でしたので、新入社員研修の際に、上で挙げた「現在価値」などの考え方について簡単なレクチャーを受けたことがありましたが、その当時はあまり理解が進まず、その後だいぶ時間が経った後に、法務部への相談における文脈の中でこの本を使って学んだことで、ようやく本質的な理解が得られたように思います。
この本は「ファイナンスの本質とはつまり何なのか?」を丹念に掘り下げて書かれていますので、法務部員が読む本としてちょうどいい内容であると感じました。
本質的な理解さえ得られていれば、相談時の受け答えが不自然になるようなことはないと思われます。あとの細かい知識はとりあえず無視していいと思います。
ファイナンス以外でも知っておくべきと感じた知識(教養という言い方でもいいかもしれません)についても、別の項で紹介していきたいと思います。
本項は以上のとおりです。



コメント